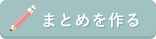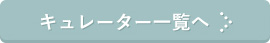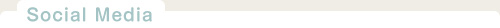黄体機能不全の場合、生理周期が短くなりやすい傾向にあります。
月経初日から次の月経の前日までの日数(月経周期)は、25日〜38日が正常範囲とされていますが、黄体機能不全の場合は、排卵後の黄体期(高温期)が安定して持続せず、極端に高温期が短いまま月経が起こってしまうことがあります。
生理不順
黄体機能不全の症状
黄体機能不全とはその名の通り、黄体が上手く機能せず、黄体ホルモン(プロゲステロン)分泌が不十分な状態を指します。
黄体ホルモンのおかげで女性の体は基礎体温が高くなり、子宮内膜も厚くなって妊娠しやすい体になります。
黄体ホルモンの分泌が少ないと、女性の体は正常な生理周期を生み出せず受精卵を受け入れる準備が整わないため、不妊症の原因になってしまいます。
黄体機能不全とは

黄体機能不全は基礎体温でわかる?
黄体機能不全による不妊は、不妊症の約10%を占めていると言われています。
黄体ホルモンの働きによって子宮内膜が柔らかく厚みのあるお布団のようになり、着床に適した環境を形成し、妊娠しない場合は内膜がそげ落ちて、月経となって体外へ排出されます。
黄体機能不全になると、子宮内膜の形成がうまくいかず、受精卵が着床しにくくなり、妊娠しにくい体になってしまうのです。
また、着床できたとしても赤ちゃんが成長する前に子宮内膜が剥がれて妊娠を維持できない「不育症」を起こすこともあります。
不妊症や不育症
生理ではないのに子宮内膜の一部が剥がれて、月経前に少量の出血が続くことがあります。
機能性出血が起こる
これらの症状がある場合は早めに婦人科を受診しましょう。
・高温期が10日以内
・高温期が途中で一時的に下がる
・低温期から高温期の以降に時間がかかる(3日以上)
・低温期と高温期の体温差が0.3度未満
・低温期が長い
黄体機能不全であるかどうかは症状から判断するよりも基礎体温で判断するほうがわかりやすいといわれています。
一般的に36.7度以上を高温期と考え、通常はこの高温期が11〜14日程続くのですが、黄体機能不全では高温期が短くなり、高温期の体温が低くなるという特徴があります。

黄体機能不全の原因
女性ホルモンはストレスの影響を受けやすいと言われています。
排卵を含む一連の体の変化が脳内の視床下部によって調節されているため、精神的ストレスや肉体的ストレスによる視床下部への影響が卵巣にも影響します。
ストレス
黄体機能不全の原因ははっきりとはわかっていませんが、いくつかの要因が指摘されています。
下半身は元々冷えやすく、子宮・卵巣の機能が冷えると機能が低下し、卵巣機能不全・黄体機能不全につながりやすいと言われています。
冷え・血行不良
甲状腺ホルモンの異常
甲状腺ホルモンに乱れがあるとホルモンバランスが崩れ、月経異常、排卵障害や黄体機能不全が起きやすいといわれています。
黄体機能不全の治療法
黄体機能不全と糖尿病の因果関係はまだ明確ではないとの指摘もありますが、糖尿病などの全身性の病気が原因で卵巣機能不全になり、黄体機能不全の症状を示すという見方もあるようです。
糖尿病
黄体機能不全の治療には、排卵誘発剤を使用して卵胞の発育不全を改善するものと、排卵後に黄体ホルモンを補充して黄体機能を維持するものなどがあります。