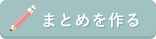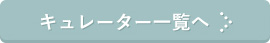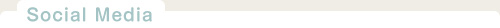なぜ停留精巣が起こるの?
また、普段は陰嚢の中に精巣があっても、腹部との間で簡単に移動する状態を「移動性精巣」と言いますが、これは思春期頃までに動かなくなるので特に治療は必要ありません。
停留精巣が見られるのは男の子の約3%で、生まれた時には停留精巣が見られてもそのうちの2/3は生後3〜4ヶ月頃までに自然に下りてきます。
なので、自然に下りてこずに治療が必要な場合は男の子のうち約0.8%程度だそうです。
停留精巣がある赤ちゃんの内、その半数は右側の精巣が停留し、1/4は両方の精巣が停留していると言われています。
精巣は通常、「陰嚢」と呼ばれる袋状の器官に入っています。
精巣は妊娠7〜8週目に作られ始め、妊娠30〜32週頃におなかの中から陰嚢の中へと下りてきます。
しかし、下りてくる途中で止まってしまうと「停留精巣」となるのです。
そもそも停留精巣って?

停留精巣であっても特に症状はありません。
しかし、精巣がお安価の中に長時間留まっていることで温度が上がり、精巣の発達が遅れてしまうこともあるようです。
精巣の発達が遅れると、精子を作る細胞が減少したり精管がうまく発育しなかったりすることで、将来的に不妊の可能性も指摘されています。
症状は?
早産や低出生体重児の場合には、停留精巣の発生率が高いようです。
また、家族の中に停留精巣だった人がいる場合にも、停留精巣が起こりやすいようです。
停留精巣の原因として、男性ホルモンの分泌不全、精巣を固定する人体の付着、鼠径部の通過障害、腹部内圧などさまざまな要因が考えられます。
しかし、停留精巣の原因のほとんどは原因の分からない突発性のものだと言われています。
治療法は?費用は?
停留精巣があるからと言って、必ずしも将来不妊になるというわけではありませんが、長い間放置することでそのリスクは上がると考えられていますので、早めに小児科を受診するようにしましょう。
また、治療せずに停留精巣を放置すると、おなかの中で精巣がねじれてしまう「精巣捻転」や「腫瘍」を発症する恐れがあります。
精巣捻転が起こると、精巣に血液が送られなくなるので栄養が運ばれなくなり、強い痛みや腫れが起こります。
早急に対応しないと、精巣が壊死し精巣腫瘍などの発症リスクも高まりますので、注意が必要です。

生まれてすぐに停留精巣だと診断されても、生後6ヶ月ころまでは様子を見ます。
陰嚢の中に精巣が下りてこず、おなかの中に留まっている場合には1歳前後に手術をして精巣を下ろす処置をします。
非触知精巣
「触知停留精巣」は精巣を足の付け根あたりに触知できる状態です。
この場合には精巣を固定する手術を行います。
下腹部にある鼠径部を2~3cm切開し、精巣についた血管や精管、筋肉をはがし、精巣を陰嚢のなかに糸で固定します。
触知停留精巣
手術費用は保険適用で数万円程度かかりますが、「乳幼児医療助成制度」によって補助を受けることが出来ることもあります。
この乳幼児医療助成制度は各自治体が医療費を助成してくれる制度です。
まずは、お住いの自治体の窓口などに問い合わせをしてみて下さい。
「非触知精巣」の場合には内視鏡検査をして、精巣の状態を確認します。
もとから精巣がないか、大きさが極めて小さく、正常に機能しない可能性もありますが、精巣の位置が確認できたら、鼠径部を切開して精巣を固定したり、萎縮してしまっている部分があれば除去したりする手術を行います。